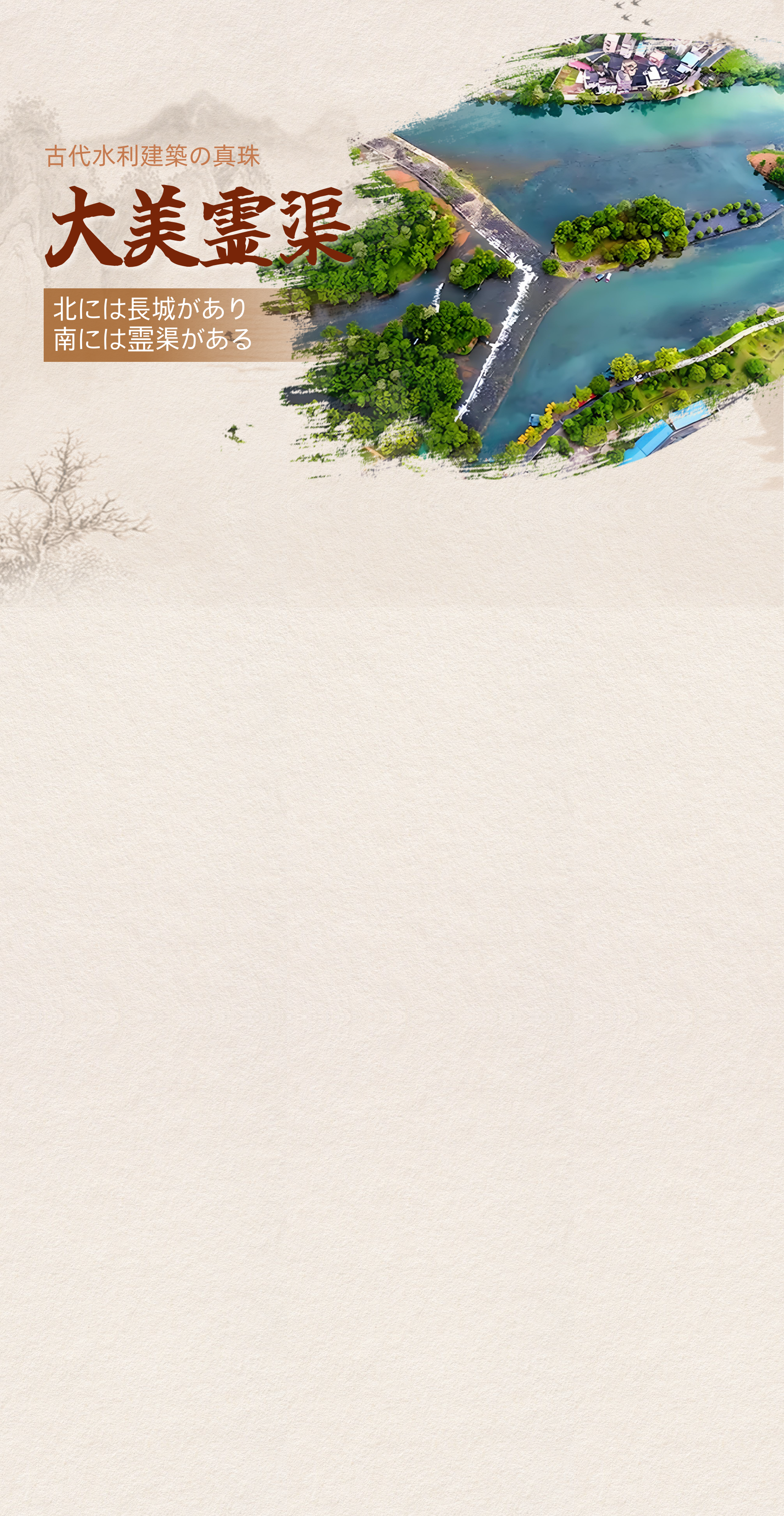霊渠(れいきょ)の建造は、直接に秦の始皇帝(しんのしこうてい)の百越(ひゃくえつ)遠征の軍事ニーズ에応えるものであり、中央王朝(ちゅうおうおうちょう)の嶺南(れいなん)統治を固めるための基盤的な工事でした。
南征の苦境を打開:戦国時代(せんごくじだい)末期、嶺南地方(現広東省・広西チワン族自治区・ベトナム北部一帯)に居住する「百越」の部族はまだ臣服(しんぷく)していませんでした。秦軍(しんぐん)が南征(なんせい)する際、南嶺(なんれい)が障壁となり、兵糧(へいりょう)の輸送は全て陸路(りくろ)に頼らざるを得ませんでした。山道(さんどう)は険しく輸送能力が低いため、「3 年間、鎧を脱がず弓を緩めなかった」という艱難な状況に陥り、軍事的な進捗は極めて遅れました。
戦略回廊を開通:紀元前 214 年に霊渠が開通した後、秦軍は長江(ちょうこう)の支流(しりゅう)である湘水(しょうすい)を経て霊渠に入り、さらに珠江(しゅこう)の支流である灕江(れいこう)に移ることで、「湘水と灕江が分流し、相互に補い合って通航(つうこう)が実現された」という目標を達成しました。水路輸送により兵糧や兵士を速やかに南方へ送ることが可能になり、秦軍は戦局(せんきょく)を急速に逆転させ、最終的に百越を平定(へいてい)して嶺南地方を正式に中央王朝の版図(はんず)に編入し、中原(ちゅうげん)と嶺南の政治的統一(せいじてきとういつ)を初めて実現しました。
長期的な軍事保障:その後、霊渠は歴代王朝(れきだいおうちょう)が嶺南を支配するための軍事通路(ぐんじつうろ)となりました。南方で反乱(はんらん)が起こったり辺境(へんきょう)の防衛(ぼうえい)ニーズが生まれたりするたびに、中央軍(ちゅうおうぐん)は霊渠を通じて兵力(へいりょく)や物資補給(ぶっしひょきゅう)を迅速に投入でき、中央による南方への軍事的抑止力(よくしりょく)を強化し、多民族国家(たみんぞくこっか)の統一を固める役割を果たしました。
霊渠は世界で最も早く長江流域(ちょうこうりゅういき)と珠江流域(しゅこうりゅういき)を貫通させた人工運河(じんこううんが)で、その工事知恵(こうじちえ)と歴史的価値(れきしてきかち)は唯一無二(ゆいいつむに)です。
水系連通(すいけいれんつう)の節目(せつもく):長江と珠江は中国南部(ちゅうごくなんぶ)の二大独立水系(どりつすいけい)ですが、霊渠は巧妙な設計(湘水を導いて灕江に合流させる)を通じて、初めて二大流域を一体に結びました。これにより中国南北水上交通(なんぼくすいじょうこうつう)の「最後の 1 キロメートル」を開通し、中原(ちゅうげん)と嶺南(れいなん)の水上輸送(すいじょうゆそう)を「隔絶(かくぜつ)された状態」から「直結(ちょっけつ)された状態」へと転換しました。
水利工事(すいりこうじ)の手本(てほん):霊渠の全長(ぜんちょう)は 37 キロメートルで、その中核技術(ちゅうかくぎじゅつ)である「陡門(とうもん)」(現代の船戸(せんこ)に相当)は世界最古(せかいさいこ)の船戸システムです。段階的(だんかいてき)に水位(すいい)を上げることで、湘水(しょうすい)と灕江(れいこう)の水位差(約 6 メートル)による通航(つうこう)の難題(なんだい)を解決(かいけつ)したこの技術は、ヨーロッパで最も早く出現(しゅつげん)した船戸より 1000 年以上も早いものです。「戸で水を節約(せつやく)し、水で船を航行(こうこう)させる」という設計は、古代の職人(しょくにん)が水文学(すいもんがく)・力学(りきがく)に対する正確(せいかく)な把握(はあく)を体现(たいけん)しており、後世(こうせい)の水利工事の手本となりました。
歴史的連続性(れきしてきれんぞくせい):秦(しん)の時代から近代(きんだい)の鉄道(てつどう)・道路(どうろ)が発達(はったつ)するまで、霊渠は南北水上輸送の幹線(かんせん)として 2000 年以上も持続的(じぞくてき)に通航してきました。中国歴史(ちゅうごくれきし)で使用期間(しようきかん)が最も長い人工運河の一つであり、その安定性(あんていせい)と実用性(じつようせい)は同時代(どうじだい)の世界の他の水利工事をはるかに凌駕(りょうが)しています。
霊渠の影響(えいきょう)は軍事(ぐんじ)と交通(こうつう)をはるかに超え、中国南方(ちゅうごくなんぽう)の発展構図(はったつこうず)をより深く形作(かたちづく)りました。
経済開発(けいざいかいはつ):通航(つうこう)が開始(かいし)された後、中原(ちゅうげん)の鉄器(てっき)・絹織物(きぬおりもの)・手工芸技術(しゅこうげいぎじゅつ)が霊渠を通じて嶺南(れいなん)へ伝わり、一方で嶺南の米(こめ)・香辛料(こうしんりょう)・真珠(しんじゅ)などの物産(ぶっさん)は北運(ほくうん)されて中原に供給(きょうきゅう)されました。これにより嶺南地域(れいなんちいき)は「未開の地(みかいのち)」から「魚米の郷(ぎょめいのさと)」へと転換(てんかん)し、南方の農業(のうぎょう)・手工業(しゅこうぎょう)の発展を加速(かそく)させました。
文化融合(ぶんかゆうごう):中原文化(ちゅうげんぶんか)(文字(もじ)・礼儀(れいぎ)・科挙制度(かきょしせいど)など)は霊渠を経て南下(なんか)し、嶺南の百越文化(ひゃくえつぶんか)と衝突(しょうとつ)・融合(ゆうごう)して、独特(どくとく)な嶺南文化(れいなんぶんか)(広東語(かんとうご)・嶺南建築(れいなんけんちく)など)を形成(けいせい)しました。これにより南方地域居民(なんぽうちいききょみん)の中央王朝(ちゅうおうおうちょう)に対する文化的帰属意識(ぶんかてききぞくいしき)が強化(きょうか)され、多民族国家(たみんぞくこっか)の結束力(けっそくりょく)を築く(きずく)ための文化的基盤(ぶんかてききばん)が整(ととの)えられました。
霊渠は優れた工事技術(こうじぎじゅつ)と歴史的価値(れきしてきかち)により、国内外(こくないがい)の学界(がっかい)から高い評価(こうか)を得ています。
都江堰(とうけんえん)・鄭国渠(ていこくきょ)と並んで「秦代三大水利工事(しんだいさんだいすいりこうじ)」と呼ばれるが、その独特(どくとく)な「流域横断通航(りゅういきおうだんつうこう)」機能(きのう)は、古代水利工事の中でも独樹一幟(どくじゅいっしょく)の存在(そんざい)です。
国際水利学界(こくさいすいりがっかい)では「世界古代水利建築の明珠」と称(しょう)えられ、その陡門(とうもん)の設計(せっけい)は「船戸の父(せんこのちち)」と見なされ、後世(こうせい)の運河工事(うんがこうじ)(例:京杭大運河(けいこうだいうんが))に重要(じゅうよう)な技術的参考(ぎじゅつてきさんこう)を提供(ていきょう)しました。
2018 年(にせんじゅうはちねん)、霊渠は「世界灌漑工事遺産(せかいかんがいこうじいさん)」に選定(せんてい)され、中国古代水利の業績(ぎょうせき)が世界に羽ばたく重要(じゅうよう)な象徴(しょうちょう)となりました。




「霊渠覧勝」は霊渠の水を脈絡とし、三つの篇に分かれてその歴史的価値を表現している。後列中央部の浮彫りが第一篇で、「嶺南統一と辺境の安定」をテーマとし、秦の始皇帝が領土を広げる背景や、監御史禄(しかんゆしろく)に霊渠を築くよう命じた情景を描いている。前列左側部の浮彫りが第二篇で、水利交通に焦点を当て、史禄(しろく)が三名の将軍と兵士たちと共に霊渠を開削した偉大な業績を語っている。前列右側部の浮彫りが第三篇で、民族の結束、安南(アンナン)の使節が通過する様子、遠景に商人たちが集まる様子などの場面をつなぎ合わせ、霊渠が古代海上シルクロードの開拓に果たした重要な貢献を描いている。
「美龄橋(びれいきょう)」は、造型が精巧な白い大理石のアーチ橋である。1941 年(昭和 16 年)8 月、蒋介石(しょうかいせき)は夫人の宋美齢(そうびれい)を伴い霊渠(れいきょ)を遊覧し、南渠(なんきょ)を渡る際、宋美齢は竹と木でできた橋の安全性が低いことに気づき、この場所に石造りのアーチ橋を建設するよう提案した。橋が完成した後、人々は宋美齢が霊渠に寄せた配慮に感謝するため、この橋を「美龄橋」と命名した。
「四賢祠(しけんし)」は別名「霊済廟(れいざいびょう)」とも呼ばれ、元 (げん)・至正 (しょうせい) 15 年(1355 年)に建造された。秦 (しん) の監御史禄 (しかんゆしろく)、漢 (かん) の伏波将軍 (ふくはしょうぐん) 馬援 (ばえん)、唐 (とう) の桂管観察使 (けいかんかんさつし) 李渤 (りぼく)、防禦史 (ぼうぎょし) 魚孟威 (ぎょもうい) の、霊渠 (れいきょ) の開削と維持に功績があった四位の賢人を祀ることから「四賢祠」と名付けられた。 この祠は、広西道粛政廉訪副使 (こうせいどうしゅくせいれんぼうふくし) ヤルギニ(也儿吉尼)が霊渠を修復する際に建設したもので、元代 (げんだい) の黄裳 (こうしょう) が撰 (せん) した『霊済廟記 (れいざいびょうき)』の石碑 (せきひ) は現在も保存されている。歴代 (れきだい) を通じて改修が繰り返され、現在の四賢祠は 1985 年に再建 (さいけん) されたものである。
この木はヤナギ科の大木(大重楊樹)で、樹齢は 780 年余りに達する。樹幹は瘤(こぶ)だらけだが、葉は青々と茂り、生気にあふれている。不思議なのは、木の幹に寄りかかっていた乾隆 12 年(1747 年)の「新装黒神・水星二像題名碑」(新しく安置した黒神・水星二神の像に関する題名碑)を、横方向に約 3 分の 1 まで「飲み込んで」いることだ —— これにより石碑は地面と平行になり、地面から約 30 センチメートル浮いた状態になっている。 現在、この石碑は既に 3 分の 1 が樹幹に取り込まれ、残りの 3 分の 2 は木の外に露出している。しかもこの木は依然として 3 年に 1 センチメートルの速度で石碑を「飲み込み続け」ており、予測によれば 200 年後には石碑全体が古樹に完全に包まれるとされる。